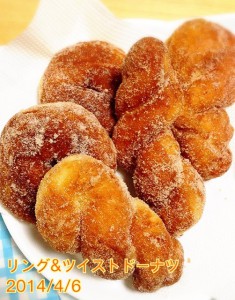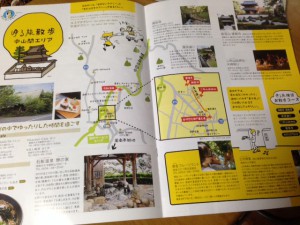こんばんは、いよいよ明日はX’masイヴ♪
今ごろ、サンタクロースは最終準備中ですかね…
さて、今年も残すところあと8日間なんですね~
大掃除、終ってる方もいらっしゃるでしょう!
私も今日は頑張って断捨離dayのつもりでしたが、うっかりひいてしまった風邪が長引き、風邪薬を飲んで、年末の貴重な休日を、終日お布団の中で過ごしてしまいました。
では、この前の続きで、今年の後半戦を振り返ってみます!
7月・・・1年のど真ん中、今年の7月1日は「うるう秒」 でした。日本時間
2015年7月1日午前8時59分59秒と午前9時00分00秒にの間にうるう秒が1秒挿入されたんでしたね!そして、つゆ明けしたこの月は、ひたすら暑さ対策をしながらの通勤でした。
8月・・・東日本大震災復興応援プロジェクトとして、被災地の方々中心に参加を募集した「スポーツひのまるキッズ柔道親子夏合宿」を、宮城県仙台市の東北高校の柔道場をお借りして開催。朝飛大先生、佐藤愛子先生、原沢久喜先生を特別講師にお迎えしての合同練習会、保護者向けには上野雅恵・順恵姉妹の母、上野和歌子さんからご自身の子育てのお話を聞いたり、その他、栄養セミナー、コーチングセミナー、親子ふれあいヨガ教室、最後は楽しくBBQ大会で終りました。我々スタッフは、東京からワンボックスで移動。私は初めて、東北道をロングドライブ。交代しながらですが、かなり運転しがいのある道のりでした。運転のごほうびの牛タンランチ、本当に美味しかった!

9月・・・東海大会と四国大会のダブル開催で、準備中も大混乱するほど、濃~い一ヶ月でした!!
10月・・・嵐のような9月が去り、ひたすら2大会分の残務に追われながらも、次の北信越大会の準備を頑張りました。
11月・・・北信越大会の前日は、大会に参加したご家族も一緒に、きっときと市場内のレストランでの懇親会。射水市市長、連盟の先生、協賛社の方々、特別講師のみなさんも、豊富な海産物を中心のおごちそうに舌鼓!楽しい時間を過ごしました。
大会当日は青井久幸先生、藤田博臣先生、佐藤愛子先生、地元富山出身の安達春樹先生のご指導での柔道クリニック。
12月・・・中国大会の開催、ついこのあいだだったんですよね!柔道イベントの特別講師は、朝飛大先生、青井久幸先生、真壁友枝先生、手島桂子先生、地元山口出身の河原正太先生。先生方のご指導に真剣な眼差しをむける子供たちの眼差し。試合会場内での柔道イベントは、試合の熱気と勝負の一喜一憂で熱く、暖房いらずの一日でした。撤収後、いつもなら帰路に急いでいるところ、中国大会は翌朝帰りなので、スタッフで夕食に。美味しい焼肉と冷え冷えの生ビール、めっちゃ旨旨でした。

今年の後半戦も、慌ただしく日々が過ぎ、一年間が一瞬でした!なんとか年内に風邪を治し、頑張って大掃除をして、スッキリと新年を迎えたいと思います♪♪♪
ひのまるキッズ事務局 丸山